ブルータス(2019年2月1日号)の特集記事「おいしいコーヒーの教科書2019」をパラパラと眺めていると、あのレストランでおいしいコーヒーをという記事が目に留まりました。
コーヒーメニューですが、街中のレストランには欠くことの出来ない必要不可欠なドリンクメニューのはずです。何といっても、付加価値が高い(儲けさせてくれる)わけですから。
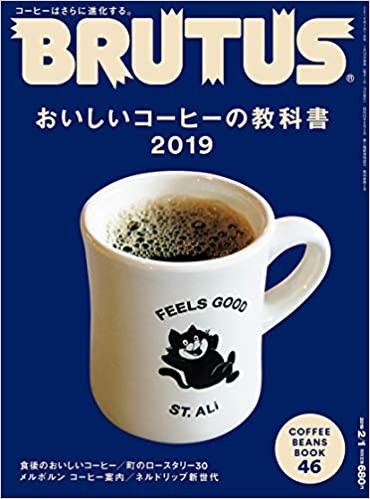
特に、朝食・昼食をメインとするレストランのドリンクメニューは、コーヒーが中心になるはずです。
鎌倉市のあるレストランがお客さんに提供するコーヒーは、コーヒー豆を自家焙煎している近所の喫茶店に特注した焙煎コーヒー豆を使って淹れていると、あのレストランでおいしいコーヒーをの記事中で紹介されています。
コーヒーは付加価値の高い(儲けさせてくれる)ドリンクメニューですから、手抜きしてはダメということをほのめかしている記事だと肯定的に捉えています。
地域の独立系レストランが生き残って行くためのキーワードは、「ローカルフード」と「手づくり」だとする意見もあります。(小生も、そのように考えています)
手づくり・少量生産・新鮮な焙煎コーヒー豆を使って淹れたコーヒーが、街中のレストランで提供され始めているのだと思います。
コーヒー豆の焙煎とコーヒーの醸造は一体のものですから、コーヒーに熱中すれば、当然、コーヒー豆の自家焙煎に行きつきます。しかし、街のレストランにコーヒー豆焙煎機を設置するスペースの余裕も、コーヒー豆を焙煎する時間的余裕も無いはずです。
そこで、次善の策として登場して来るのが、同じ地域の自家焙煎珈琲店とパートナーの関係を構築するという方法です。
おそらく、先駆け的な独立系レストランは、今後、その方向に進んで行くのだろうと考えています。(ブルータスも、そう考えているのだと推測しています)
2000年代に発生した北米大陸のサードウェーブコーヒー現象は、街で飲むコーヒーに使う焙煎コーヒー豆が、大規模な焙煎工場で焙煎加工したコーヒー豆から少量生産・手づくりの焙煎コーヒー豆にシフトした結果として発生した現象だと理解しています。
大量生産した焙煎コーヒー豆を使っていた街中のレストランや喫茶店・ホテルが、スターバックスコーヒーに代表される喫茶店チェーンとの差別化が必要になって、手づくり・新鮮・少量生産のサードウェーブコーヒー系ロースターの焙煎コーヒー豆に一斉に切り替えた結果、新しい焙煎コーヒー豆市場が開拓されて小規模ロースターが急成長した現象をサードウェーブコーヒーだと考えています。
簡単に表現すれば、街のレストランや喫茶店・ホテルが、焙煎コーヒー豆の購入先を大手・中堅ロースターから地域のコーヒー豆自家焙煎店に切り替えたので発生した現象だと考えているわけです。
ブルータス(2019年2月1日号)の特集記事「おいしいコーヒーの教科書2019」
は、日本でも、北米大陸で発生したサードウェーブコーヒー現象のような文化が発生する可能性があると語っているように感じられます。

